荻窪のおっちゃんの
自腹で「名著」を紹介
コピー依頼は受けられません。ご理解くださいませ。m(_ _)m
エフェクター自作&操作術 VERSION 3.1
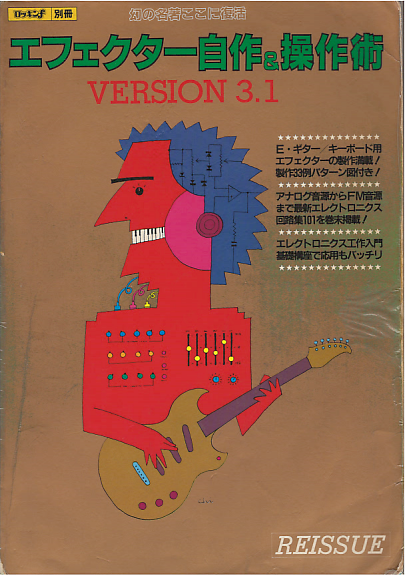
| 著者 | 浜田 雅生、井上 ヒデキ、沖田 訓明、向井 朗、峰 雅彦、堤 光生、 秋山 桂三、大野 祥之、竹内 常夫、国本 利文、阿部 敏之、大塚 明、山口 郁準、松本 浩之、六角 文雄ほか(順不同、敬称略) |
| 出版社 | 株式会社 立東社 (倒産したようです・・・。「リットーミュージック」との関連性はよくわかりません。) |
| 出版日・発行日 | 1987年(昭和62年)9月10日発行 |
| 値段 | 2,800円 |
| その他 | 絶版。全274ページ。裏表紙では本のタイトルがなぜか「ロッキンf別冊●ミュージック・マシン・ハンドクラフトV3.1●」になっています。 |
この本が生まれた背景には、「エフェクターは高価だから自作する」という、切実な時代の要請があったに違いありません。欲しければ作るしかない状況下での「自作」は、理屈抜きに合理的であり、そこに情熱を傾けることに一片の迷いもなかったはずです。しかし、私がこの本を手にした1987年、エフェクターは既に「作るもの」から「買うもの」へと変貌を遂げていました。安価で高品質な製品が溢れる時代において、「自作」に合理性はなく、情熱にも躊躇が生まれるのは必然です。それでもなお、私はこの本に込められた「自作への情熱」に、抗いがたい魅力を感じるのです。「自作」が必然であった時代の、あのひたむきで熱狂的な情熱は、現代においては失われてしまった、一種のロマンなのかもしれません。
蛇足ですが、この本の「C-MOSドライバー(オーバードライブ)」などでC-MOSのインバータ(NOT素子)にフィードバックをかけて歪を得ていますが、C-MOSはバッファー・タイプはダメで、アンバッファー・タイプでなくてはいけません。バッファー・タイプを使うと良い音はしますが、すぐに壊れます(→「C-MOSオーバー・ドライブ回路」を参照してみて下さい。)。 もしもこの本を手に入れて自作する人がいたら気をつけて下さい。
| 項目 | ★ | コメント |
|---|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ | 内容は高度です。電気・電子の知識があれば確かな読み応えがあります。 |
| 初心者歓迎度 | ★★★ | 初心者を置いていかない配慮をしていますが、そもそもレベルの高い本なので・・・。 |
| 作成手順の親切度 | ★★★★★ | はんだ付けやエッチングの知識(と道具とお金と時間)があれば、ほぼ作例どおりに作成できます。 |
| 時代マッチ度 | ★ | 古い本なので部品の一部は販売中止になっています。現在入手可能なものへの部品の置き換えにはそれなりの知識が必要です。 |
| エンタメ度 | ★ | エフェクター自作の「実用書」としての側面が強いです。 |
Rock音!アナログ系ギター・エフェクタ製作集
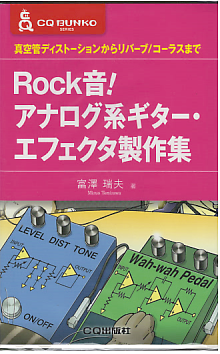
| 著者 | 富澤 端夫(敬称略) |
| 出版社 | CQ出版株式会社(CQ BUNKO SERIES) |
| 出版日・発行日 | 2020年(令和2年)4月15日発行 |
| 値段 | 1,400円+消費税 |
| その他 | 2023年11月現在、新品で入手可能。全271ページ。 サブタイトルとして「真空管ディストーションからリバーブ/コーラスまで」が付いています。 |
当時、これらの記事を網羅するために、私はかなりの数の『トランジスタ技術』を購入し、その保管場所に頭を悩ませていました。しかし、この一冊にまとまったことで、長年の悩みが解消され、部屋もすっきりと片付きました。
エフェクター製作に興味のある方にとって、貴重な情報が凝縮された、まさに保存版と言えるでしょう。
アナログ・エフェクタがメインで取り上げられます。しかし、 デジタル・ディレイICのPT2399を扱った記載もあったりします。
この本は、エフェクターの「製作」というよりも、むしろその「原理解説」に重点が置かれているようです。そのため、具体的な製作手順のみを知りたい読者にとっては、少しハードルが高いかもしれません。
表紙の親しみやすい雰囲気から、初心者向けのハウツー本だと誤解してしまうかもしれませんが、実際はそうではありません。電気・電子に関する一定の知識を持つ読者が、さらに深い理解へと進むための道標となることを意図して書かれているように感じます。
つまり、この本は、エフェクター製作の入門書ではなく、より高度な知識を求める読者のための専門書と言えるでしょう。
エフェクターは既成品で十分という風潮の中、 今後こういう本が出版される可能性は低いのではないかと思います。 絶版になる前に手に入れておくのが良いかもです。 大きめの書店に行けば普通に売っていますし、アマゾンでも手に入ります(2023年11月現在)。
| 項目 | ★ | コメント |
|---|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ | 内容は高度です。電気・電子の知識があれば確かな読み応えがあります。 |
| 初心者歓迎度 | ★ | 初心者に電気・電子技術の基礎知識の重要性を認識させる本ではあります。 |
| 作成手順の親切度 | ★ | ある程度自作の経験がないとこの本を基に自作はできないでしょう。 |
| 時代マッチ度 | ★★★★ | フェイザーの回路図で生産中止になった2SK30を使用しており、ほんの少しだけ時代にマッチしていません。代替品はわりと容易に手に入るので深刻な問題ではないです。 |
| エンタメ度 | ★ | この本にエンタメは不要です。 |
じ★いんすつるめんつ骨董不可思議えれき箱
| 著者 | 文:大塚 明、協力:小沢 靖、イラスト:佐原 輝夫(敬称略) |
| 出版社 | リットーミュージック |
| 出版日・発行日 | 1980年代後半?〜1990年代前半? |
| 値段 | - |
| その他 | リットーミュージックの「Guitar Magazine」に不定期で載っていた記事群です。 その後、記事をまとめたものが出版されたようです。絶版ですが、著者の大塚氏がサイト「珍品堂アナログ店」にてCD-ROM形式で有料配布しておられるようです。 「珍品堂アナログ店」で検索すればサイトにたどり着けます。 |
その記事は、毎回、懐かしのエフェクターをテーマに、その製作方法を指南するものでした。「珍品堂」主人と「懐古軒」主人の掛け合いで展開される斬新なスタイルは、読み物としても面白かったです。
私もこの記事のファンで、掲載されるたびに切り抜いて大切に保管していました。しかし、引っ越しの際にうっかり手放してしまい、今手元に残っているのは第八話の「オートワウ」のみとなってしまいました。それでも、時々読み返しては、あの頃の興奮を思い出しています。
| 項目 | ★ | コメント |
|---|---|---|
| 充実度 | ★★★★★ | 電気・電子の知識があればさらに楽しめます。 |
| 初心者歓迎度 | ★★★★★ | 初心者を退屈させない配慮があります。 |
| 作成手順の親切度 | ★★★★★ | はんだ付けとエッチングの知識(と道具とお金と時間)があれば、ちゃんと作れます。 |
| 時代マッチ度 | ????? | 執筆時で手に入らない部品については代替品が提示されています。しかし、その執筆も30年ほど前なので代替品もどの程度手に入るのか私にはわかりません…。 |
| エンタメ度 | ★★★★★ | 私の知る限り、技術とエンタメを両立させた唯一のエフェクタ製作記事です。 |